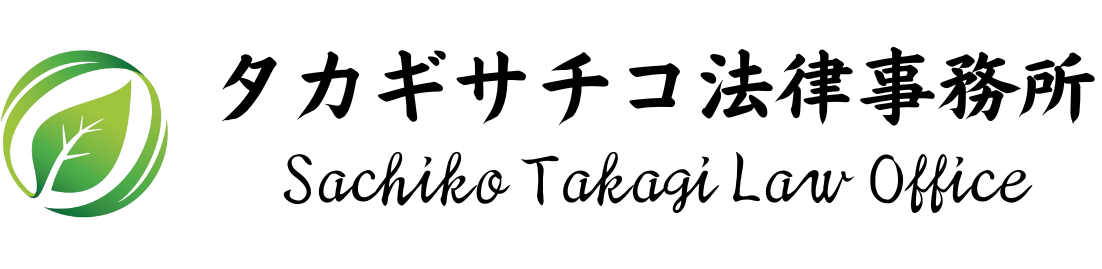このページでは、相続に関する一般的な事例をご紹介します。
似たような状況の事例をご確認いただくことで、起こり得るトラブルを事前に把握しやすくなります。
なお、ここで扱う事例は、一般的な解説を目的としたフィクションです。登場人物は実在しません。具体的な案件については、必ず弁護士にご相談ください。
遺産分割に関するトラブル事例
次に示す事例は、遺産分割が円滑に進まないことにより生じやすいトラブルを取り上げたものです。専門家の助言やサポートを受けることで、多くのトラブルは予防・解決が可能です。
遺言書の解釈
故人が残した遺言書の内容や意図が明確でない場合、相続人の間で解釈が分かれ、トラブルに発展することがあります。
エピソード①
故・田中太郎氏は遺言書を残して亡くなりました。遺言書には「私の貯金は息子の一郎に、マンションは娘の花子に譲る」と簡潔に記載されていました。
一郎は、父の貯金額が1,000万円であることを知っており、その全額を受け取るものと考えていました。ところが、太郎氏の死後、花子が「父の貯金の半分は私のものだ」と主張しました。花子は、遺言書の「息子の一郎に」という文言は「貯金の全額」ではなく「貯金の半分」を一郎に与える趣旨だと解釈したのです。
また、花子はマンションの管理費や固定資産税についても、一郎に半分負担してもらうべきだと考えました。一郎はこれに反論し、遺言書の内容は明確であると主張しましたが、花子は「父は兄妹の公平を考えていたはずだ」と反論しました。
このように、簡潔な表現の遺言書が原因で一郎と花子の意見が対立し、最終的には専門家の助言を求めることになりました。
本エピソードは、遺言書の表現が簡潔すぎる場合、相続人の間で解釈が分かれ得ることを示しています。遺言書を作成する際には、分配の範囲や割合、費用負担等も含め、できる限り具体的に記載することがトラブル回避の重要なポイントとなります。
エピソード②
故・中村一郎氏は、遺言書に「私の所有するアパートは長男の誠に、私の預金は300万円を次男の浩史に、残額は三男の竜三に相続させる」と明確に記述して亡くなりました。
この遺言書に基づき家族は相続手続きを進めましたが、問題が生じました。浩史が預金通帳を確認したところ、預金の合計が250万円しかなく、遺言書に記載された金額より50万円少なかったのです。
浩史は、預金が減っている理由を調べるうち、竜三が生前に特定の大きな支出を手伝っていたという情報を得ました。浩史は「竜三が父の預金を無断で使用したのではないか」と疑い、竜三に50万円の支払いを求めました。これに対し竜三は、預金を使ったこと自体は認めつつも「父の了承のもとでの出費であり、無断ではない」と反論しました。
このように、遺言書の内容が具体的であっても、実際の資産状況と一致しない場合、相続人間の不信感が生まれ、対立が深まることがあります。
本エピソードは、遺言書の内容と現実の資産状況の不一致が、トラブルの原因となり得ることを示しています。
遺言書の有効性
遺言書が法的に有効かどうかをめぐる争いです。方式(手続)の不備や、故人の意思表示が適切であったか(意思能力・自由意思)に疑義が生じる場合などがあります。
エピソード①
田中夫妻は長年子どもに恵まれず、晩年に養子を迎えました。養子となったのは、夫妻が長年面倒を見てきた甥の純一でした。
田中夫妻は老後を純一とともに過ごし、純一を実の子のように思っていました。ある日、田中夫人は自筆証書遺言を作成し、家の金庫に保管しました。遺言書には「私の財産はすべて純一に相続させたい」と記載されていました。
数年後、田中夫妻は相次いで亡くなりました。純一は遺言書を見つけ、これに基づいて相続手続きを進めようとしました。しかし、血縁の遠い親族である美紀が反発し、「遺言書は夫人が純一に影響されて書かされたものだ」と主張しました。さらに、美紀は日付の記載が曖昧であることや、一部の筆跡が夫人のものと異なるように見えること等を理由に、法律上の方式や夫人の判断能力に問題があるとして、遺言書の無効を主張しました。
これに対し純一は、弁護士を通じて、遺言書が夫人自身の筆跡であることを示す資料や、作成当時の診療録・介護記録、近隣の知人やかかりつけ医の証言等を収集し、夫人に意思能力があり自由意思に基づいて作成したことを主張しました。あわせて、遺言書が法律上の要件を満たしていることも説明し、遺言書の有効性を争うことになりました。
本エピソードは、遺言書の有効性、とりわけ「方式要件」や「意思能力・自由意思」をめぐって、親族間でトラブルが生じ得ることを示しています。遺言書を作成する際は、方式を満たすことに加え、作成経緯が後から疑われないよう、保管方法も含めて専門家の助言を受けておくことが有効です。
エピソード②
佐藤昌夫は長年、小さな会社を経営してきました。息子の大輔は家業を継ぐ意思がなく、都会でIT関連の仕事をしていました。一方で、娘の菜々子は会社を手伝い、将来は後を継ぐことを望んでいました。
ある日、昌夫が突然の事故で亡くなり、遺族が書類を整理する中で、10年前に作成された遺言書が見つかりました。遺言書には「私の会社と私のすべての資産は、息子の大輔に譲る」と記載され、日付や署名押印もありました。
しかし、ここ10年ほどの昌夫の言動からは、むしろ菜々子を後継者として信頼し、実務や意思決定を菜々子に任せる場面が増えていました。従業員や取引先も「いずれ菜々子が会社を継ぐのだろう」と受け止めていたほどでした。
そのため、遺言書の内容と近年の状況との間に大きなギャップが生じ、家族間で対立が起きました。菜々子は「父の最終的な意思は自分に会社を継がせることだった」と主張し、大輔は「遺言書に基づき自分が承継するのが当然だ」と主張しました。
遺言書は形式上の要件を満たしていても、作成から長期間が経過し、家族関係や事業状況が変化していると、感情面・実務面の双方で紛争が生じやすくなります。最終的には、遺言書の内容を前提にしつつ、遺留分や会社の運営継続も踏まえた調整が必要となり、弁護士を通じた交渉や法的手続へ進むことになりました。
本エピソードは、遺言書が古いこと自体で無効になるわけではない一方、事情が変わった場合に「遺言の内容が現状に合わず」争いの火種となり得ることを示しています。考えや状況が変化したときには、遺言書を見直し・更新しておくことが、紛争予防の観点から重要です。
生前贈与の取り扱い
故人が生前に一部の相続人へ財産を贈与していた場合、その贈与を遺産分割でどのように扱うか(特別受益として持ち戻すか等)について、相続人間で意見が分かれることがあります。
エピソード①
中山優子は夫とともに田舎で静かに暮らしていました。優子には2人の子どもがいて、長男の健は地元で家を継ぎ、次男の修は都会でIT企業に勤めていました。優子の夫は10年前に亡くなり、その後は息子たちと過ごしていました。
数年前、修が一時的に多額の資金を必要とした際、優子は支援のために自宅の隣の土地を修へ贈与しました。贈与契約書を作成し、名義変更登記も済ませたため、その土地は修の名義となりました。修はその土地を担保に資金を調達し、後に借入れを返済しました。
優子の死後、遺産として残っていたのは自宅の土地建物や預貯金などで、隣の土地は修名義のため遺産には含まれていませんでした。ここで健と修の間で意見が分かれました。
健は「隣の土地は生前に修が受け取った利益であり、兄弟間の公平のため、特別受益として考慮すべきだ」と主張しました。つまり、隣の土地の価値を持ち戻して計算し、残りの遺産を分けるのが妥当だと考えたのです。
一方、修は「贈与は資金調達を助けるための支援であって、相続分の前渡しではない」と反論しました。借入れも返済しており、土地は仕事を続けるための基盤である以上、遺産分割で不利に扱われるのは納得できないと主張しました。
このように、生前贈与を特別受益として持ち戻すべきかどうかをめぐり、遺産分割協議が難航することとなりました。
本エピソードは、生前贈与の目的や性質(生活援助か、相続分の前渡しか等)が明確でないと、遺産分割で対立が生じ得ることを示しています。生前贈与を行う際は、目的や取扱いを家族で共有し、可能であれば書面化し、必要に応じて専門家に相談しておくことが有効です。
エピソード②
桐山家は老舗の和菓子屋を営んでおり、当主の一郎と、長女の真紀、次女の悠里がいました。真紀は家業を手伝い、将来の承継も視野に入れていました。一方、悠里はアーティストとして独立し、スタジオを構えて活動していました。
数年前、悠里がスタジオを開設する際、一郎は支援のために貯蓄の一部を贈与しました。悠里はその資金を元にスタジオを設立し、作品制作を続けていました。
一郎が亡くなると、遺産には和菓子屋の土地・建物、設備、個人的な貯蓄等が含まれていました。真紀は「悠里はすでに生前贈与を受けているのだから、その点を考慮して遺産分割すべきだ」と主張しました。これに対し悠里は「贈与は創作活動の支援であり、相続分の前渡しではない。遺産分割では平等に扱うべきだ」と反論しました。
このように、生前贈与を遺産分割でどのように評価するかについて意見が一致せず、話し合いが難しくなることがあります。
本エピソードは、家族内の生前贈与が、贈与の意図や評価をめぐる認識の違いから、遺産分割のトラブルにつながり得ることを示しています。
不動産の評価
故人が遺した不動産について、どの評価額を基準にするか(時価・路線価・固定資産税評価額等)で見解が分かれ、遺産分割が難航することがあります。特に、市場価格との乖離がある場合や、将来的な価値変動(再開発・用途変更等)が見込まれる場合は対立が生じやすくなります。
エピソード①
中島家は山間部に広大な土地を所有していました。その土地は数十年前までは果樹園として利用されていましたが、近年は放置され、樹木が生い茂る状態になっていました。中島家の当主・信雄が亡くなった際、遺産にはこの土地も含まれていました。
信雄には2人の子どもがおり、長男の和也は都会で不動産関連の仕事をしていました。次男の浩史は地元で農業を営んでいました。
浩史は「地元の相場を基準に評価して分割すべきだ」と考えました。自分は将来的に農地として活用する意向があり、現状の利用実態に合った評価が適切だと感じていたためです。
一方、和也は「周辺でリゾート開発の計画が進んでいる以上、将来の上昇可能性も踏まえた評価で分割すべきだ」と主張しました。不動産取引の経験から、この土地の将来的な価値を見込んでいたのです。
このように、評価の基準や前提(現状重視か将来性重視か)が噛み合わず、兄弟の意見は大きく対立し、遺産分割の交渉が難航することとなりました。
本エピソードは、不動産の将来価値や地域性、利用目的などをめぐる評価の違いが、遺産分割トラブルにつながり得ることを示しています。
エピソード②
田村家は、都心部の商店街に古くからある町家を所有していました。町家は賃貸物件として利用されており、2階にはアートギャラリー、1階には老舗の和菓子屋が入居していました。
家長の一成が亡くなった際、遺産にはこの町家も含まれていました。一成には3人の子どもがいて、長女の真理は都内でデザイナーとして活動し、次女の紗織は別の都市で事業を営んでいました。三男の誠は地元に残り、和菓子屋の経営を継ぐことを望んでいました。
真理は、周辺の再開発計画の影響で将来的に土地の価値が上がる可能性があると考え、「将来性を踏まえた評価が必要だ」と主張しました。紗織も同様に再開発の情報を把握しており、真理の意見に同意しました。
一方、誠は町家への愛着が強く、家族の歴史や事業の継続を重視していました。そのため「過去の取引事例等を踏まえた現在の相場で評価すべきだ」と主張し、高めの評価には慎重な姿勢を示しました。
このように、再開発による価値変動の見込みと、事業継続や感情的価値観が重なったことで、評価額をめぐる意見が割れ、遺産分割協議が難航することとなりました。
本エピソードは、再開発等による将来の価値変動や、土地・建物に対する考え方の違いが、不動産評価をめぐるトラブルにつながり得ることを示しています。
特別な思い出や感情的価値
故人の遺した品物や財産に特別な思い出や感情的価値がある場合、金額的な価値以上に相続人のこだわりが強くなり、遺産分割が難航することがあります。
エピソード①
佐藤家には、代々受け継がれてきた古いアコースティックギターがありました。このギターは、先祖が戦時中に手に入れたもので、家族の団欒の場でよく弾かれていたことから、家族にとって特別な思い出の品でした。
佐藤家の家長・修一が亡くなった際、遺産の中にこのギターも含まれていました。修一には2人の子どもがおり、長男の健二は都内で音楽家として活動し、次男の英樹は地元でカフェを経営していました。
健二は専門家に鑑定を依頼し、アンティークとして一定の価値があることを知りました。しかし健二にとっては、祖父が弾いていた「思い出の楽器」であることが何より重要でした。
一方、英樹もこのギターを大切に考えていました。英樹はカフェでのライブイベント等でギターを使用し、祖父の歴史やストーリーをお客さまに伝えることで、店の魅力を高めたいと考えていたのです。
2人ともギターを手放すことを望まず、「どちらが所有するか」をめぐって意見が折り合わず、遺産分割の交渉は難航することとなりました。
本エピソードは、品物に対する感情的価値や思い出の重みが、金額的価値以上に遺産分割へ影響し得ることを示しています。
エピソード②
中村家には、故人・真弓が亡くなる数年前に購入した小さな置物がありました。この置物は、真弓が子どもたちと海外旅行に行った際に購入したもので、家族にとってその旅行の思い出を象徴する品でした。
真弓には3人の子どもがおり、長女の千晴、次女の佳乃、長男の直樹がいました。千晴と佳乃は、「この置物は真弓が直樹に特別な思いで贈ったものだ」と考え、直樹に譲るべきだと主張しました。母との最後の海外旅行で直樹が選んだ品であり、直樹への愛情が込められていると感じていたためです。
しかし直樹は、「この置物は3人全員の思い出を象徴するものであり、特定の誰かだけのものではない」と考えていました。そのため直樹は、置物を売却し、その代金を3人で均等に分ける案を提案しました。
置物の取り扱いをめぐって3人は感情的になり、遺産分割の話し合いは難航することとなりました。
本エピソードは、特定の遺産に対する家族それぞれの思い出や価値観の違いが、遺産分割の対立につながり得ることを示しています。
遺留分請求
遺言や生前贈与などにより、遺留分を下回る取り分しか得られない相続人が、遺留分侵害額請求(遺留分請求)を行うことで、相続人間の対立が生じることがあります。
エピソード①
鈴木家の当主・一郎は、長年会社を経営し、相応の資産を築いていました。一郎には2人の子どもがおり、長男の健太と次女の明美がいました。明美は20年前に家族との関係が悪化して家を出て以降、長く連絡を取っていませんでした。
一郎が遺言書を作成した際、健太が家業を継ぐことを前提に、資産の大半を健太に承継させる内容としていました。その結果、明美が受け取れる遺産はごくわずかとなっていました。
一郎の死後、健太が遺言書の内容を明らかにすると、明美は強い衝撃を受けました。明美は「家を出ていたとしても、法律上保障される最低限の取り分は受け取るべきだ」と考え、遺留分侵害額請求を行う意向を示しました。
一方、健太は「父の意思を尊重すべきだ」として明美の請求に反対し、兄妹の対立は深まりました。話し合いでは折り合いがつかず、結果として弁護士を介した交渉や法的手続へ進むこととなりました。
本エピソードは、遺留分請求が遺産分割に影響を与え、家族間の対立が法的紛争へ発展し得ることを示しています。
エピソード②
田中家は、都心に広い土地と一軒家を持つ裕福な家庭でした。田中家の当主・昭三は、先妻との間に息子・大輔がいました。先妻の死後、後妻との間に娘・紗矢香が生まれ、昭三は紗矢香を特に可愛がって育てていました。
昭三が亡くなった後、遺言書が見つかりました。その内容は、大輔には事業と一部の資産を、紗矢香には都心の土地と家を遺すというものでした。ところが、この遺言の結果、紗矢香の取得分が遺留分を下回る可能性があるとして、紗矢香が不公平感を抱く事態となりました。
大輔は「父の意思を尊重したい」と考えましたが、紗矢香は「たとえ遺言があっても、法律上保障される最低限の取り分は確保したい」として、遺留分侵害額請求を検討しました。
家族間で意見が分かれ、最終的には遺留分請求に関する交渉や法的手続を進めることとなりました。
本エピソードは、再婚家庭における相続関係の複雑さと、遺言内容をきっかけに遺留分請求が争点となり得ることを示しています。
相続人の確定
相続手続の前提として、誰が法定相続人に当たるのかを正確に確定する必要があります。戸籍の調査が不十分であったり、疎遠な親族の存在が後から判明したりすると、遺産分割が進まずトラブルに発展することがあります。
エピソード①
佐藤正男は60歳で亡くなりました。正男には、法律上の婚姻関係はないものの40年以上同居していたパートナー・優子と、20年前から連絡が途絶えていた娘・美智子がいました。
正男の死後、遺産分割の話し合いを進めるなかで、優子は「長年生活を共にしてきたのだから、相続についても何らかの権利があるはずだ」と主張しました。一方、美智子は「法律上の配偶者ではない以上、相続人には当たらない」として反論しました。
さらに美智子は、「父から、私には異母兄弟がいるかもしれないと聞いたことがある」と話しましたが、相手の所在や詳細は分からない状況でした。
その結果、相続人が確定するまで遺産分割を進めることができず、戸籍の調査や法的整理が必要となりました。
本エピソードは、同居していたパートナーの扱いや、未判明の相続人の存在により、相続手続が複雑化し得ることを示しています。
エピソード②
中島悟は、3人の子ども(一郎、二郎、三子)を持つ72歳の男性でした。悟が突然の事故で亡くなった後、子どもたちの間で遺産分割の話し合いが始まりました。
遺産には、中島家が代々受け継いできた土地が含まれていました。話し合いの途中で、三子が「父から昔、私たちの知らない異母の兄がいると聞いたことがある」と打ち明けました。その異母兄は、悟が若いころの関係で生まれた子で、長年疎遠になっていたというのです。
この話を聞いた一郎と二郎は驚き、その人物が法的に相続人に当たるのか、また相続に参加する意思があるのかが大きな問題となりました。
結局、戸籍をたどって相続人を確定し、当該人物の意向を確認したうえで分割協議を進める必要が生じ、遺産分割は一層複雑になりました。
本エピソードは、家族の間で共有されていない親族関係や疎遠な親族の存在が、遺産分割に大きな影響を与え得ることを示しています。
相続の放棄
一部の相続人が相続を放棄した場合、相続人の範囲や取り分が変わり、遺産分割の前提を組み替える必要が生じることがあります。また、放棄後に事情が変わり「やはり相続したい」として撤回・やり直しを求めることで、家族間のトラブルに発展するケースもあります。
【相続放棄の基本的なルール】
相続放棄は、「遺産はいらない」と家族に口頭で伝えたり、話し合いで取り分を主張しないと表明しただけでは、法律上の効果は生じません。相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行い、受理される必要があります。
相続放棄には原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)という期限があります。負債の有無が分からない、調査に時間がかかる等の場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。
また、家庭裁判所で相続放棄が受理された後は、原則として撤回(取り下げ)できません。例外的に、詐欺・脅迫など意思表示の重大な瑕疵が問題となる余地はありますが、いずれもハードルは高く、単に「気が変わった」「経済状況が悪化した」といった理由では、放棄をなかったことにすることは難しいのが通常です。
(補足)相続放棄をすると、その相続については初めから相続人でなかったものとして扱われます。
エピソード①
田中夫妻は、子どもの健太と麻美の4人で暮らしていたが、旅行中の交通事故で夫妻が急逝した。相続手続の中で、健太は起業の多忙さと経済的余裕から、麻美に家を守ってほしいという思いもあり、家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、受理された。
ところが数年後、健太の事業は失敗し、生活は一変する。一方、麻美は相続した財産を元に住まいの建替えや運用を行い、資産を増やしていた。健太は当時の判断を後悔し、**「相続放棄を取り消してほしい」**と主張して麻美に迫った。
しかし麻美は、放棄が受理されている以上、今さら覆すことはできないとして拒絶。健太は弁護士に相談し、例外的に取消しが認められる余地がないかを検討することになり、兄妹間の対立が表面化した。
このエピソードは、相続放棄後の状況変化が、撤回をめぐる争いに発展し得ることを示しています。
エピソード②
佐藤家は、父・一郎と子ども3人(大輔・絵里・和也)の家庭だった。一郎の死後、遺産にはアパートが含まれており、管理や名義の整理が必要だった。海外在住の絵里は日本での手続負担を避けたいとして、家庭裁判所で相続放棄を申述し、受理された。大輔と和也は、これで遺産分割と管理が進めやすくなると考えた。
ところが数年後、絵里が海外で事業に失敗し、生活が困窮する。絵里は「当時は事情をよく分かっていなかった」「今からでも相続に加わりたい」と言い出した。和也は強く反発し、大輔は家族として支援したい気持ちと法的整理の間で揺れた。
結局、放棄の撤回が難しいことを前提に、家族としての支援の在り方(援助の方法・金額・条件)を含めて、弁護士を交えて協議することになった。
このエピソードは、相続放棄が家族関係や感情面にも影響し、放棄後の紛争(または支援交渉)を招き得ることを示しています。