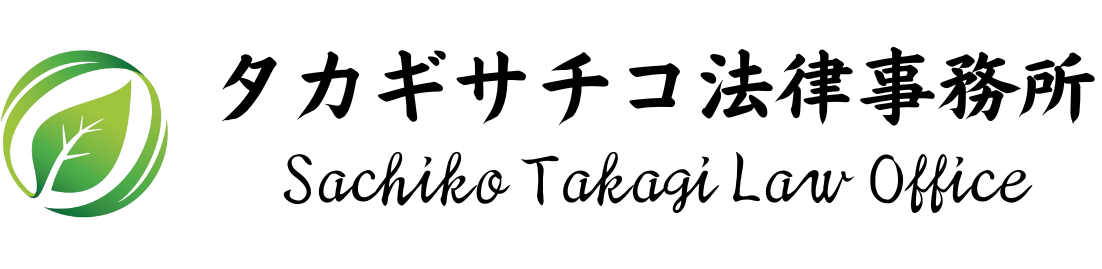【孫の遺留分請求】代襲相続・養子縁組・生前贈与が絡む「孫の遺留分請求」事案の考え方

「祖父の遺言どおりに手続きを進めていたら、孫から『自分にも遺留分があるはずだ』と言われた」
「祖父母の財産について、親ではなく自分(孫)が権利を主張できるのか知りたい」
富裕層・オーナー経営者のご家庭では、お孫さんへの教育資金・住宅資金・起業支援など、“孫への厚い支援”が行われることが多く、その結果として
- 孫が「自分にも最低限の取り分(遺留分)があるのでは?」と考える
- 他の相続人(子ども世代)や配偶者との間で意識のズレが生じる
といったご相談が増えています。
結論からいうと、
孫に遺留分が認められるケースと、まったく認められないケースがはっきり分かれます。
特にポイントになるのが、
- 親(=被相続人の子)がすでに亡くなっているかどうか(代襲相続)
- 孫が養子縁組されているかどうか
- 生前贈与や教育資金などの支援が、どの相続人の“特別受益”として扱われるか
といった点です。
この記事では、
- 孫に遺留分がある/ないケースの基本ルール
- 孫の側から取りうる法的手段と、その限界
- 祖父母・親世代としての「孫トラブル」を予防する設計ポイント
を整理していきます。
※本記事は一般的な解説であり、個別案件については、弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
孫に「遺留分」はあるのか?まず押さえたい基本ルール
遺留分とは何か──「最低限の取り分」を保障する仕組み
まず前提として、遺留分(いりゅうぶん)とは何かを簡潔に押さえておきます。
- 被相続人(亡くなった方)が、生前贈与や遺言で財産を自由に動かしすぎると
- 残された家族の生活が成り立たなくなるおそれがあるため
- 民法が「一定の相続人に、最低限ここまでは残してあげてください」と保障している取り分
これが遺留分の基本的なイメージです。
ラフに言えば、
「たとえ遺言で『全財産を特定の人に渡す』と書かれていても、
本来相続人になれるはずだった家族には、これだけは取り戻せますよ」
という“最後のセーフティネット”と考えると分かりやすいと思います。
誰に遺留分が認められているのか(孫の法的なポジション)
民法上、遺留分を持つことができるのは、原則として次の人たちです。
- 配偶者
- 子(直系卑属)
- 子がいない場合の父母などの直系尊属(上の世代の親・祖父母)
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹を代襲した「甥・姪」にも遺留分はありません。
では、孫はどうかというと──ここが本記事の核心です。
孫は、次のどちらの立場に立つかによって、扱いが変わります。
- 親がすでに亡くなっており、「親の立場」を引き継いでいる孫
- 代襲相続人として、親と同じように遺留分が認められるケースがある
- 親が健在で、孫はあくまで「子のさらに下の世代」にとどまる孫
- 原則として、孫自身には遺留分はない
この「どちらのポジションにいる孫なのか」を最初に確認することが、とても重要です。
孫が遺留分を持つケース/持たないケースの大枠
ここで、孫に遺留分が認められる/認められない大枠を先に示しておきます。
✅ 孫に遺留分が認められる代表的なケース
- 被相続人の子(=孫の親)が、
- 被相続人より先に亡くなっている(先死亡)
- 相続欠格・廃除などで相続権を失っている
- その結果として、孫が「代襲相続人」として相続人になるケース
この場合、孫は
「本来であれば親(被相続人の子)が持っていたはずの相続分・遺留分を、そのまま引き継ぐ存在」
と位置づけられます。
したがって、代襲相続人となった孫には、親と同じ割合の遺留分が認められると理解されます。
(例)
- 祖父が亡くなった時点で、長男(孫の父)はすでに死亡
- その長男の子である孫A・孫Bが代襲相続人になる
→ 長男が本来持っていた遺留分を、A・Bが人数で分けて承継するイメージ
❌ 孫に遺留分が認められない代表的なケース
- 親(被相続人の子)が健在で、親が相続人となるケース
→ この場合、孫は相続人の立場に立たないので、遺留分も発生しない - 親が相続放棄をしただけのケース(欠格・廃除とは異なる)
→ 相続放棄の場合、孫への代襲相続は起きず、結果として遺留分も発生しない - 被相続人と血縁関係はあるが、養子縁組などをしておらず、法定相続人にならない孫
このように、孫の遺留分は、
「孫だから自動的にある/ない」ではなく、
“どの立場で相続人になっているか”によって決まる
というのが重要なポイントです。
孫が遺留分を主張できる代表的なケース
ケース1:親がすでに亡くなっており、孫が代襲相続人になる場合
孫に遺留分が認められる、いちばん典型的なパターンが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。
- 祖父(被相続人)が亡くなる
- 祖父の子(=孫の親)が、すでに死亡している/欠格・廃除となっている
- その結果、孫が親に代わって相続人となる(代襲相続人)
この場合、孫は直系卑属として相続人となり、親が本来持っていたはずの遺留分をそのまま引き継ぐとされています。
イメージとしては、
「長男が受け取るはずだった相続分・遺留分を、その子どもたちが人数で分けて引き継ぐ」
という形です。
具体例
- 祖父:Aさん
- Aさんの子:長男Bさん(すでに死亡)、長女Cさん(存命)
- Bさんの子:孫Dさん・Eさん
この場合、
- Bさんが生きていれば、Aさんの相続人は「BさんとCさん」
- しかしBさんが亡くなっているため、「Dさん・Eさん・Cさん」が相続人
- Dさん・Eさんは、Bさんの持つはずだった相続分・遺留分を人数で分ける
という構図になります。
このパターンでは、「孫に遺留分がある」と言える典型的な事案になります。
ケース2:複数の孫がいる場合の「遺留分のシェア」の考え方
代襲相続が起きると、孫の数によって遺留分がシェアされる点も重要です。
さきほどの例でいえば、Bさんに子どもが3人いれば、
- Bさんが持つはずだった遺留分の枠を、
- 孫3人で頭割りする
という形になります。
富裕層相続では、
- 祖父の財産:不動産・自社株・金融資産などが数億〜数十億円規模
- 代襲相続により孫が複数人いる
- そのうちの誰かだけが生前から厚く支援を受けている
といった事情が絡み、「誰がどれだけの遺留分を持っているか」「特別受益をどう扱うか」が争点になりやすくなります。
孫には遺留分が「原則としてない」場面と、その勘違いパターン
親が生存しており、孫は法定相続人にならないパターン
一方で、多くのケースでは孫に遺留分はありません。
代表的なのが、
- 被相続人の子ども(孫の親)が生きている
- その親が相続人になっている
という状況です。
この場合、相続人は「子ども」であり、孫は相続人ではありません。
遺留分は「兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・直系卑属・直系尊属)」に認められる制度なので、
そもそも相続人でない孫には遺留分が発生しません。
「孫だから当然に遺留分がある」
という考え方は、ここでいったん整理する必要があります。
養子縁組していない孫・連れ子などの扱い
さらにややこしくなるのが、
- 実質的には家族として扱われてきたが、法的な親子関係がない孫・連れ子
- 祖父母からすれば「うちの孫同然」「ほとんど家族」というケース
です。
- 養子縁組をしていない孫・連れ子は、
被相続人(祖父母)との間に法律上の親子関係がないため、
法定相続人ではなく、遺留分も持ちません。
もちろん、遺言や生前贈与によって財産を受け取ることはできますが、それは被相続人の「好意による贈与」や「遺贈」の世界であり、
「孫の遺留分」として当然に保障されている取り分ではない
という点は押さえておく必要があります。
「孫への生前贈与=孫の遺留分」という誤解
富裕層のご家庭では、
- 孫の学費・留学費を祖父母が負担
- 孫夫婦の住宅購入資金を祖父母が援助
- 孫の起業資金を祖父母が出資・貸し付け
といった「孫への厚い支援」がよく見られます。
こうした支援は、原則として祖父母の自由意思による贈与であり、
そのこと自体が「孫の遺留分」になるわけではありません。
むしろ実務上は、
「孫に対して行われた支援が、他の相続人の遺留分を侵害していないか」
という形で、他の相続人側から問題視されることが多いのが実情です。
- 孫への多額の生前贈与
- 孫名義の口座を使った「実質的な子どもへの贈与」
- 教育資金・結婚資金の特別扱い
などは、他の子ども・孫から見ると「不公平感」の源泉になりやすく、
のちのち遺留分侵害額請求や遺産分割の場面で、
「特別受益」の議論につながることがあります。
【立場別】孫の側から取り得る法的手段と限界
孫が代襲相続人となる場合に検討できること
孫が代襲相続人として相続人になっている場合には、
親と同じ立場で遺留分侵害額請求を検討できます。
具体的には、
- 祖父母の遺言や生前贈与によって、
自分の遺留分が明らかに侵害されている - 遺産の範囲や評価額が不明確で、遺留分が侵害されているか判断できない
といった場合に、
- 遺産の範囲・評価(不動産・自社株・金融資産等)を確認
- 代襲相続人としての法定相続分・遺留分の割合を算定
- 遺留分侵害額請求(※現在は金銭請求が原則)を検討
という流れで対応していくことになります。
孫が相続人ではない場合に検討できること
一方、孫が相続人ではない(親が生きているなど)場合には、
孫自身として遺留分を請求することはできません。
この場合に孫が検討できるのは、
- 祖父母からの遺贈・死因贈与がないかの確認
- 生前の「約束」やメモ・メールなどが、
法律上どのような意味を持つか(死因贈与契約等)
などですが、法的にはかなりハードルが高く、
現実的には任意の話し合いによる解決を目指すケースが多くなります。
「遺留分ではなく、別の論点」で争う場合
「孫の遺留分」と言いつつ、
実際には次のような論点が中心になることもあります。
- 遺言無効(認知症・意思能力不足・強迫等)の主張
- 遺言の解釈を巡る争い(文言があいまいな場合)
- 親世代を通じた特別受益・寄与分の評価(親がどれだけ援助を受けていたか 等)
これらは、すべて法的には「遺留分」とは別の土俵の話です。
孫として何か納得がいかないことがある場合でも、
「これは本当に遺留分の問題なのか?」
「それとも、遺言無効・特別受益など、別の論点なのか?」
を整理することが、戦略を考えるうえで非常に重要になります。
【祖父母・親世代向け】孫とのトラブルを予防するための設計ポイント
富裕層に多い「孫への厚い支援」が生む火種とは
祖父母としては、
- 「かわいい孫に、できるだけのことをしてあげたい」
- 「教育だけは妥協したくない」
という思いから、
- 高額な私立・海外留学の費用負担
- 住宅購入資金・起業資金の援助
- 孫名義の口座に多額の資金を積み立てる
といった支援を行うことがあります。
しかし、他の子ども・孫から見ると、
「あの孫だけ優遇されているのではないか」
「親の代(子ども世代)も含めて、トータルで見ると不公平では?」
という感情的な不満につながりやすく、
のちのち遺留分侵害額請求や遺産分割トラブルとして表面化することがあります。
遺言・信託・保険・贈与をどう組み合わせるか
「孫にも何か残したい」という思いと、
「他の相続人の遺留分を侵害しないようにしたい」という要請を両立させるためには、
- 遺言(公正証書遺言)
- 生前贈与(教育資金贈与・結婚子育て資金贈与等の制度活用を含む)
- 生命保険(受取人を指定する形)
- 家族信託・遺言信託 等
を全体設計の中で組み合わせることがポイントになります。
特に富裕層の場合、
- 自社株
- 大規模な不動産
- 事業用資産
など、単純に「均等に分ける」ことが難しい資産が多いため、
「誰に・どの資産を・どのスキームで・どのタイミングで渡すか」
を、専門家と一緒に「設計図レベル」で組み立てることが重要です。
「孫養子」スキームを用いるときの注意点
相続税対策として、
- 孫を養子にして法定相続人の数を増やし、相続税の負担を軽減する
という「孫養子」スキームが取り上げられることがあります。
たしかに、一定の税務メリットはありますが、
- 他の孫・子どもから見て「特別扱い」に映りやすい
- 法定相続人としての地位を与えることで、
遺留分・遺産分割の場面で発言力が大きくなる - 家族関係が複雑な場合、感情的なしこりを残すリスクがある
といった感情面・家族関係のリスクも無視できません。
「税金が減るから」という理由だけで採用するのではなく、
- 一族として、誰をどのように位置づけたいのか
- その子・孫にどの程度の責任と権限を持たせたいのか
といった長期的な視点で判断することが重要になります。
実務的な対応ステップ:「孫の遺留分請求」への向き合い方
Step1:誰が相続人か・孫の法的ポジションを正確に確認する
まずは、
- 被相続人の戸籍・除籍謄本
- 家族関係図(祖父母・子・孫)
をもとに、
- 誰が法定相続人なのか
- 孫が代襲相続人になっているのか、それとも相続人ではないのか
を正確に確認します。
ここを誤解したまま議論を進めると、
「本当は遺留分がないのに、ある前提で話が進んでしまう」
ということになりかねません。
Step2:遺言・生前贈与・生前の約束の有無を整理する
次に、
- 遺言書の有無・内容(公正証書か自筆か)
- 孫やその親世代への生前贈与・援助の履歴
- 生前の約束(メモ・メール・手紙など)があるか
を整理し、「事実関係の土台」を固めます。
この段階で、
- 遺留分侵害が現実的に問題となる余地があるか
- むしろ特別受益・寄与分・遺言無効など別の論点が中心か
が、おおよそ見えてきます。
Step3:孫の主張が「遺留分」なのか、別の法的主張なのかを切り分ける
孫から
- 「自分にも遺留分があるはずだ」
- 「祖父は自分にも残すつもりだった」
といった主張が出てきた場合でも、
- それが代襲相続人としての正当な遺留分主張なのか
- あるいは遺言無効・特別受益・任意の配慮を求める声なのか
を切り分ける必要があります。
ここを整理せずに感情論だけで応酬してしまうと、
家族関係の修復が難しくなってしまいます。
Step4:話し合いでの着地点を探るのか、法的手続きも視野に入れるのか
最後に、
- 家族内の話し合いで一定の着地点を探るのか
- 調停・訴訟などの法的手続きも視野に入れるのか
を、法的リスクと家族関係のバランスを見ながら判断していきます。
富裕層・事業オーナーの場合、
- 金額が大きい
- 係争期間が長引くほど、事業や一族のレピュテーションにも影響する
といった事情があるため、
「法的には勝てる可能性が高いが、あえて任意の解決を選ぶ」
という選択肢も、現実的なオプションとなり得ます。
弁護士に相談すべきタイミングと、準備しておきたい情報
早めに専門家のサポートが必要になるサイン
次のような兆候が見られたら、
早めに弁護士への相談を検討すべきタイミングといえます。
- 孫側から、弁護士名義の内容証明が届いた
- 「遺留分侵害額請求」「訴訟」「調停」といった具体的なワードが出てきた
- 他の相続人(子ども世代)との関係も悪化し、一族全体の空気が重くなっている
- 事業の後継者選びや株主構成に影響が出そうな事案である
この段階では、一つひとつの対応が後の展開を左右する局面に入っていることが多く、
専門家のサポートを受けることでリスクをコントロールしやすくなります。
相談時に整理しておきたい事項
相談前に、可能な範囲で次のような情報を整理しておくと、
初回相談がスムーズに進みます。
- 家族関係図(祖父母・子・孫の関係)
- 被相続人の死亡日・年齢・職業・主な資産構成
- 遺言書の有無・内容(写しがあれば持参)
- 孫やその親世代への生前贈与・援助の概略(いつ・誰に・いくら程度)
- 孫とのやり取り(メール・LINE・手紙など)の記録
これらをもとに、弁護士は
- 法的にどこまで「権利の問題」として争う余地があるか
- どのあたりに「現実的な落としどころ」がありそうか
を、より具体的にアドバイスしやすくなります。
まとめ──「孫の遺留分請求」は、家族関係と資産戦略の両面から考える
孫の遺留分の有無は、「孫だから」ではなくポジションで決まる
- 孫に遺留分が認められるのは、
代襲相続人として子どもの立場を引き継いでいる場合に限られます。 - 親が健在で孫が相続人になっていない場合、
孫自身には遺留分はありません。
「孫だから当然に遺留分がある」という発想は、一度リセットする必要があります。
富裕層だからこそ「感情」と「権利」を分けて設計する重要性
- 孫への厚い支援(教育・住宅・起業資金など)は、一族としての喜びである一方、
他の相続人の遺留分や感情とのバランスを欠くと、将来の火種になりかねません。 - 法律上の権利だけでなく、
一族全体の関係・事業承継・評判などを見据えた「資産戦略としての相続設計」が必要です。
早い段階からの相談が、一族全体のダメージを最小限に抑える
- 「孫の遺留分請求」という言葉が出てきた時点で、
それが本当に遺留分の問題なのか、別の論点なのかを整理することが第一歩です。 - そのうえで、
- 法的リスク
- 家族関係
- 事業・資産戦略 を総合的に見ながら、早めに専門家に相談することが、
一族全体のダメージを最小限に抑えるための近道になります。